連載<もう一つの「発達のなかの煌(きら)めき」>第5回解説版
2022年8月
白石 正久・白石 恵理子
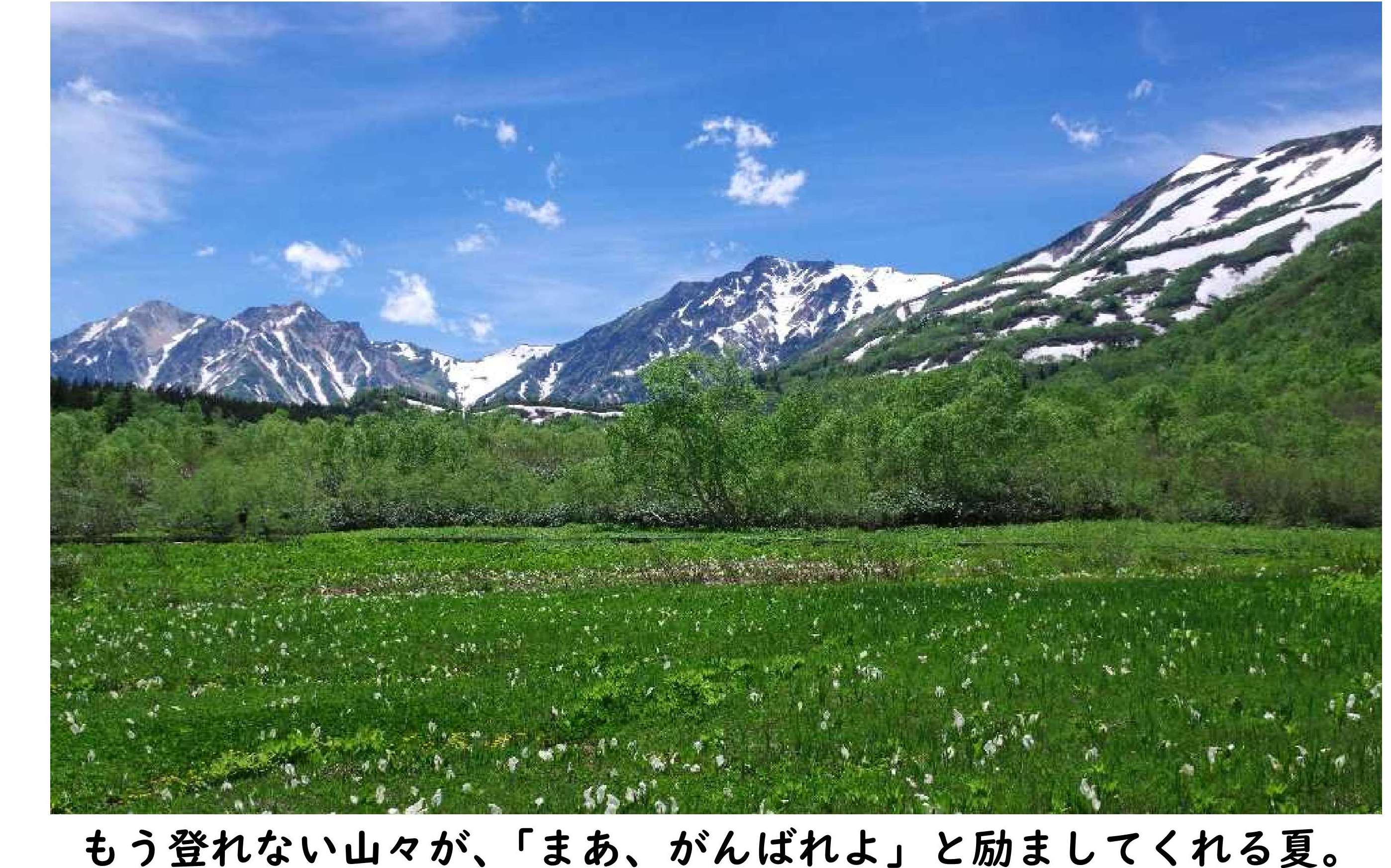
第5回 1歳半の発達の節(その2)
連載第5回(8月号)の「『本当の要求』とはなにか ― 自閉症児と『一歳半の節』」では、横軸に私たちの発達相談という仕事を通して考えた、地域で暮らす、生きるということの発達にとっての意味を、縦軸に「1歳半の節」における発達の障害をとりあげました。
変化する素材と道具
8月号では、「1歳半の節」において「Aの次にはB」「Cの上にはD」などと言う時間的空間的な「むすびつき」が先行し、それゆえに思いや期待にそわない現実とぶつかりながら、「…ではない…だ」と思考して「切りかえる」可逆操作を獲得していくことができると述べました。この「1次元可逆操作」の獲得が、運動、活動、対人関係、話し言葉、自我などの発達の土台として大切な役割を果たすことを、「もう一つ」第4号とともに、『新版・教育と保育のための発達診断・上巻』(以下では『上巻』)の「Ⅲ
2章 1歳半の質的転換期と発達保障」「Ⅳ 自閉スペクトラム症と発達診断」、『新版・教育と保育のための発達診断・下巻』(以下では『下巻』)の「Ⅱ
3章 1歳半の質的転換期の発達と発達診断」で深めていただければと思います。
そして、自閉スペクトラム症(以下では自閉症)は、この可逆操作の獲得に発達の障害が現れることも述べました。この傾向は自閉症に限られず他の障害、あるいは障害はなくても「発達の偏り」として起こりやすいものです。
「もう一つ」第4号のなかに「はめ板回転課題」の解説があります。
1歳すぎの子どもたちは、さっきと同じように目の前の孔に入れようとするのですが、それでは円板は入りません。「入っていない」ことに気づいて、怪訝な表情になったり、四角孔の上でカタカタさせたり、検査者をじっと見たり…なかには、立ちあがってしまう子もいれば、入っていなくても「気にしていない」子もいます。そのうち、「ここじゃないのかな…」とばかりに、別の孔にチャレンジしようとしたり、円板をひっくり返してみたり、なかには基板の下から入れようとしたりと、様々な試行錯誤をはじめます。これらは、いずれも検査上は「不通過」、「できない」と評価される姿なのですが、そこには1次元可逆操作を我がものとしようと努力する大切なプロセスが潜んでいるのです。

子ども本人は円孔に入れようとする自分なりの「つもり」の達成のために一生懸命なのですが、この「さまざまな試行錯誤」を近くで見守る人はイライラするものです。だから、「そこじゃないでしょ」と言葉をかけたり、手を出してしまったりするかもしれません。きっとそういったことは、子どもを混乱させる役割しか果たしません。「…ではない…だ」と状況のなかで自分を切りかえたり、調整していくためのかけがえのない「自分づくり」をしているのであり、その自由で主体的な活動を心から応援し、見守りたいと思います。1歳前半の子どもは、その「入れ切る」ことを目的とはしておらず、むしろ「…ではない…だ」のリハーサルを重ねているようにもみえます。そのリハーサルの豊かさをみるためには、「はめ板」ではなくて、もっと自由度があって、さまざまに操作できる素材や道具の方がよいはずです。
保育所の砂場で遊ぶ0,1歳児の姿を見てください。片手にコップをもち、砂をすくってはひっくり返し、両手にコップをもって一方のコップですくった砂を他方のコップに移しかえ、スコップですくった砂を器に入れてはひっくりかえし…。「1歳半の節」の前後において、子どもは変化する素材と道具の創り出す活動に魅入らされていきます。

そういった自由度を発揮できる発達検査にしようと、田中昌人さん、田中杉恵さんは、「器への積木の入れ分け課題」を考案しました。8月号の30ページの写真です(『子どもの発達と診断2』大月書店、また『下巻』85ページ)。1歳前半では、まだ「…ではない…だ」が内面化していないために、一方の器に8個すべての積木を入れてしまいます。しかし、他方の器がカラであることに気づいて、その器に全部の積木を移しかえます。そしてまた、カラになったもとの器に移しかえることを繰り返します。この移しかえで、まさに「…ではない…だ」のリハーサルをしている感じです。
1歳後半になると頭のなかで考えて、一つあるいは少しの積木を左右の器に「コチラではないアチラだ」と配分していくのです。子どもは、自由に操作できる素材と道具であるゆえに、単に自由であるだけではなく、移しかえたり重ねたりと、発展性のある活動を展開するでしょう。しかも、1歳後半になれば、相手の意図を受けとめて配分を試みたことを意識しており、自分なりの入れ分け方をした器を、相手に「どうぞ」という感じで差し出してくれるようになります。自分のなかで「…ではない…だ」を操作するだけではなく、相手の意図を引き受けて、自分の意図として応え返すという自他のあいだでの可逆操作もみることができるでしょう。「もう一つ」の次号で扱いますが、「1歳半の節」を越えて2歳になる頃には、ていねいな入れ分けを行なわなくなり、一方にたくさんの積木を入れて、他方に残りの少しの積木を入れるようになります。そういった「重みづけ」を創り出すようになるのが「二次元の世界」の入り口の姿です。
変化する素材への抵抗を乗り越える
変化する素材の代表例として、砂場の「砂」をとりあげました。皆さんのなかには、自閉症のある子どもの嫌いなものの一つだと思われた方もいるでしょう。手につき、新奇性のある素材は、彼らの教材として好ましくないと言われることもあります。
私たちは、そのことを固定的にみてはならないと考えてきました。『上巻』の「Ⅲ 2章 1歳半の質的転換期と発達保障」で述べましたが、砂遊びの輪に入ろうとしなくても、「外れていない外れ方」「なかまにはいっていく手がかりを遠くに示した外れ方」「やりたい思いを高めつつも、ドキドキしながら背中でようすを窺っている外れ方」をしているようにみえることはないでしょうか。
このような「行動は見えないけれど、心がみえる」という評価は、昨今の特別支援教育では、客観的な証拠がないとして「書き直し」を求められると聞きました。しかし心の動きは、誰であっても外に表れ出るとは限りません。その見えない心理を大切にして、わかりあい、互いを尊重していこうとみんな努めていると思います。障害のある子どもの心の動きは、「見える」ものだけで評価するのでしょうか(目で見えるときには「見える」、心の目でみえるときには「みえる」と、私たちは表記します)。
証拠は、時間の経過のなかで子どもが示してくれます。ある日、気がつけば砂場の近くに寄ってきている子どもの姿があったりします。手のひらに載せた砂を「だいじょうぶ、だいじょうぶ」と応援しながらそっと差し出すと、指先で触って、走って行ってしまうかもしれません。でも気がつけば、また近寄ってきています。そうやって、気持ちを支えてもらい、ときには先生に勇気を引き出してもらって、一つひとつの矛盾、葛藤を、この子らも乗り越えていくのです。そのときの指先には、しだいに勇気が満ちていくようです。

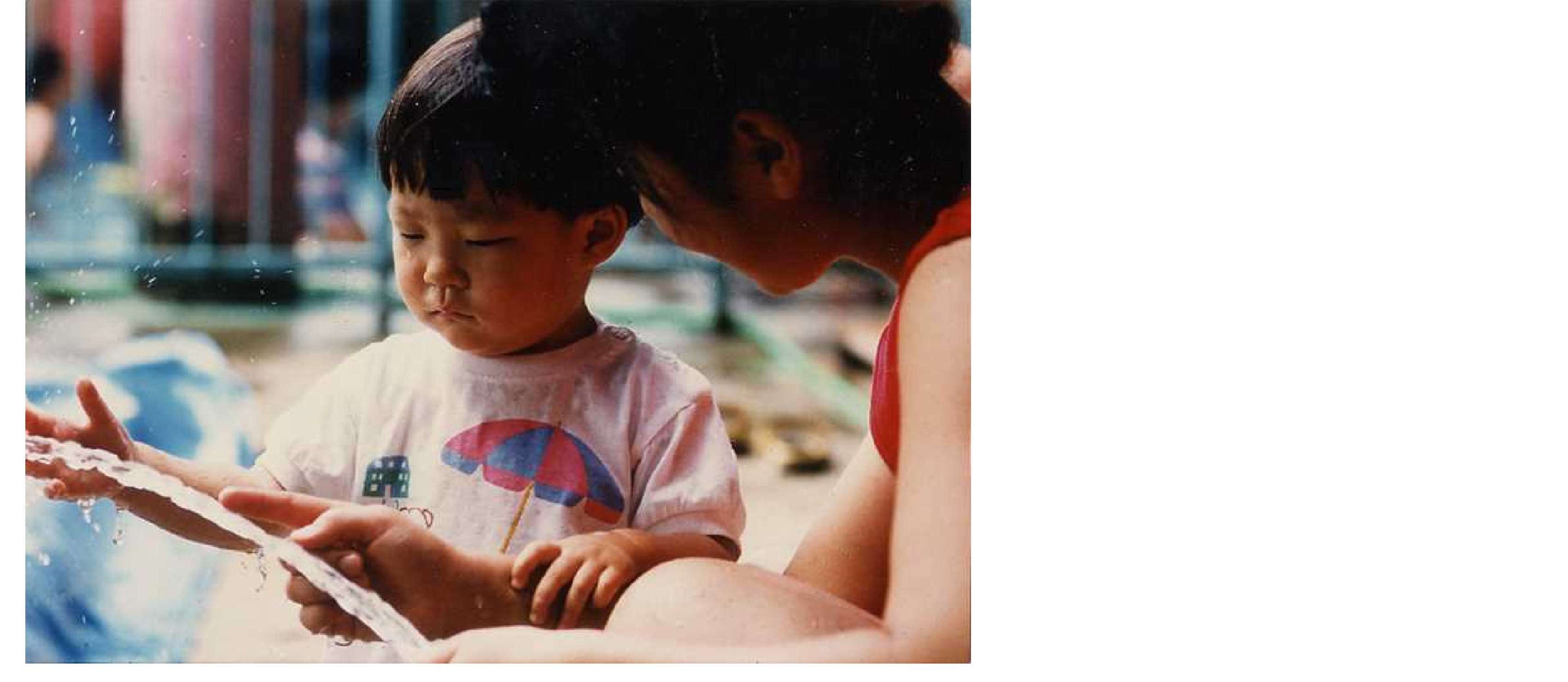
変化する素材への興味は、砂ばかりではなく、いろいろなものに拡がっていきます。手で触れたときの変化の喜びを、いっしょに抵抗を乗り越えた人とまなざしを交わしあって共有するようになっていきます。子どもは、素材にはたらきかけていくなかで、「…ではない…だ」と変化を創り出し、またその変化から「…ではない…だ」という可逆操作を、自らのなかに豊かに取り込んでいきます。変化する素材で、「…ではない…だ」という1次元可逆操作のリハーサルをしているようなものなのです。
「1歳半の節」で、器やスコップ、スプーンや櫛などの道具の意味を発見していくと、変化する素材へのはたらきかけはいっそう豊かになり、生活で憧れたことを手がかりに、プリンを作ったり、ごはんをよそったり、「みたて・つもり」遊びもできるようになるでしょう。
こういった素材や道具への興味は、年齢や経験の拡がりとともに変化していくものです。そのときの社会的関係のなかで意味をもつものに、心惹かれるようになります。8月号のコウジくんのように、牛乳瓶を洗う、野菜を袋詰めにするという広い生活経験に依拠したものに変化していくのです。
だから乳幼児期には乳幼児期でしか味わえない素材や道具とのふれあいがあります。10か月頃の「生後第2の新しい発達の力」が誕生するときには、砂や水などの変化する素材に指先でそっとふれて抵抗を乗り越えていきます。その指先が散歩で出会ったアリや小鳥、花などに伸びて、指さしとしての機能をもつようになります。そして、他者とともにその変化や発見を喜び、「第二者と第三者を共有する」関係を形成していくのです(白石正久「乳幼児の生活の組織化と発達保障」『障害者問題研究』第50巻2号、最新刊)。そして、音や色の変化を楽しむ感覚玩具よりも、生活のなかで見かける道具に興味をもつようになります。
児童発達支援は、利用契約制度になってから、「○○療法」を名乗る看板を掲げて利用者を集める動きのなかにあります。細切れの時間単位のなかで、「はめ板」をそのまま教材化したような「パズル」に取り組んでいるところもあると聞きました。そういった事業者は、乳幼児期の通園施設、通園事業、児童デイサービスが積み上げてきた発達保障の実践を知りません。狭い空間や短い時間での活動ではなく、土や砂、水、畑の作物などの変化する素材に、先生や友だちとともにからだをいっぱい使ってはたらきかけ、散歩で出会う生命あるもの、人びとの暮らしの姿に瞳を輝やかすような実践を、ぜひ知ってもらいたいと思います。そしてそういった実践が、心置きなく取り組める制度に改めていきたいものです。
幸福感においてつながる
8月号で、「1歳半の節」では、次のような発達がみられると書きました。
「対」の人間関係、つまり「わたしとあなた」において、自分の意図と他者の意図、自分のモノと他者のモノという自他を区別し、対立・葛藤しつつ調整ができはじめる(30ページ)。
自閉症のある人たちは、「他者」の意図を意識すること、それができるようになっても、他者の意図と自分の意図を調整することがむずかしく、混乱や拒否、あるいは従属や指示待ちという関係になりがちです。しかし、このことも決して固定的ではないことを、私たちは発達相談や実践の過程から認識してきました。
8月号で、コウジくんの姿を通して以下のように書きました。
最初に訪問したときに商店主がその仕事をしており、彼に手伝わせてくれたようです。そのていねいさにびっくりされたのでしょう。彼にとっては、そう受けとめてもらえたことがうれしかったのです(29ページ)。
コウジくんも洗瓶のエピソードにおいて、自分の挑戦をまるで我がことのように喜び、幸福感において他者とつながれる人がいるのだと実感したのでしょう。閉じてしまった活動や人間関係が未来に向かって開かれていく実感であり、そのことによって生活に「はりあい」を感じるようになっていったのだと思います(31ページ)。
この「幸福感においてつながる」とはどういうことでしょう。それは、発達の過程のなかに、そして日々の暮らしのなかに、その大切さを認識することができます。
・「第二者と第三者を共有する」
「生後第2の新しい発達の力」が誕生する10か月頃、子どもは自ら発見した生命のあるものを指さしで教えてくれ、入れたり、渡したり、放ったりの定位的活動ができ始めます。しかしまだ、そのことが他者の喜びや怒りにつながるとはわかっていません。「きれいなお花ねぇ」「じょうずやなぁ」「ありがとう」「そんなことしたら、アカンよ」などという言葉を添えられた他者の反応から、その意味をだんだん理解できるようになるのです。
すでに述べたように、このように「第二者」という大切な人と何ごとかを共有できるようになっていくことを、「第二者と第三者を共有する」と言います(田中昌人・田中杉恵)。心理学では、「三項関係」と言われますが、それでは子どもの主体性が表現されていません。10か月頃は、その「第二者」がこれまでの限られた関係から、他のおとな、そして友だちへと普遍化し、拡がり始める段階でもあります。そうやって新しい他者とつながったとき、子どもは本当にうれしそうです。その幸福感があるからこそ、もっと他者とつながって生きたいという、次の時間や空間への期待や要求が確かになっていくのでしょう。
・日々の暮らしのなかで
この「第二者と第三者を共有する」ことによって生まれる幸福感は、日々の暮らしのなかでかけがえのない姿として育まれていきます。
かつて『発達をはぐくむ目と心』(24~32ページ)で、深見憲『ひろしくんの本Ⅰ~Ⅶ』(中川書店、1999~2017年)を紹介しました。
「あの時の物凄い博の形相を思い出すだけで胸が痛み一生忘れることは出来ません。この時を契機に家族はどんな些細な興味の世界でも博の世界の中にどっぷりつかって楽しんで守っていこうと誓いました」(『ひろしくんの本Ⅳ』2004年、26ページ)。
博さんは、現在55歳になった自閉症のあるかたです。お母さんの憲さんが、その成長・発達と生活の過程を、『ひろしくんの本』として刊行されてきました。4歳のときにプレイセラピーの先生から「生活の内容を改善していくため」に、「こだわり」の対象となっているクラシック・レコード、おとぎ話のレコードや本を隠してしまって、戸外で思い切り遊んであげなさいという指導を受けました。その通りに庭の物置に隠してしまった日、「奇声と泣きわめきのすさまじいパニック」になり、食事も受けつけず、瞳もうつろになった姿を目の前にして、「これから好きなレコードをいっぱい聞こうな。毎日、博の好きなことをいっぱいしよう」と言いながら、お父さんはレコードと本を物置から持ち帰ったそうです。「自分たちの一方的な身勝手な押し付けをしてきたことを反省」させられ、いつまでもわが子の「瞳の輝き」が失せない生活をはぐくんでいきたいと決意したと綴られています。そのことが、後の家族の生き方の礎になったとも言われます(『ひろしくんの本
Ⅶ』、2017年)。
「興味の世界こそ自閉症児の至福の時であり遊びの世界である。付きあってあげるという感覚の方々には幼稚な世界と片づけられるが、年を追うごとに奥が深く夢の広がる世界はとても楽しいのである」(「成人期」『そだちの科学』第1号、日本評論社、2003年)。
「付きあってあげるという感覚の方々」は、胸に痛い言葉です。自閉症のある人たちが、心地よさ、楽しさ、なにごとかを成し遂げた喜びなど、さまざまな幸福感を求めていること、しかしそれ以上に状況や他者と自分がむすびつきがたく、悲しみ、苦しみをもって生きる時間が長いことを私たちは感じています。私たちもそうだと思うのですが、自他つまり「わたしとあなた」の関係でいろいろな齟齬や葛藤はあっても、それを乗り越えて共感できる関係が欲しいし、我がことのように受けとめあえる人とつながりながら、日々を生きたいのです。
自閉症のある人たちが示す行動、「特性」と呼ばれるもの、その背景にある発達の連関の「ずれ」は、本人の生きづらさの要因でもあります。それらは現実に存在しており、それを理解しようとすることは大切なことです。しかし同時に、それが「彼らは私たちと違う」という認識に留まってしまうことはないでしょうか。私たちは、ものごとを「違い」において理解する癖をもっていることを否定できません。困難をもちつつ、それを乗り越えて生きようとする人の精神、心理を、人間としての普遍性・共通性において理解しようとしなければ、「してあげる」「してあげなければならない」「はたらきかける」などと、心の離れたところから、あるいは高みから関わるようなことになってしまうと思うのです。そのことが、指導や支援の前提としての子どもを理解すること、子どもと関係をむすんでいくことを困難にしていることはないでしょうか。
成人になった博さんは、「第九を歌う会」に参加し、ケーキやクッキーを作って販売する「プティフールヒロシ」を開き、子どもたちへのおとぎ話の紙芝居の上演へと、地域の人びととの関係を拡げていきました。すべてが幼児期の「興味の世界」に根ざしています。今は、社会福祉法人の運営する食堂で、長く憧れであった食器や調理具の洗浄の仕事をして働かれているそうです。家族は、小さいときから「よくできました」ではなく「ありがとう」と受けとめあう関係を大切にして、ともに歩まれてきました。
地域の人びととのつながりは、自分の活動、仕事、そして存在そのものの意味を実感できる関係です。何ごとかを創造する喜びが、それを手にしてくれた人の喜びにつながったとき、明日もまたがんばろうと、未来に開かれた希望をもって生きることができるのだと思います(8月号、31ページ)。
地域、生活、労働と発達をつなぐ
療育や教育は、子どもの発達要求を踏まえ、「めあて」をもってはたらきかけ、子どもたちの姿から、さらに指導をつないで発展させていくという「時間の単位」をもった営みです。
一方、子どもやなかま、その家族は、家庭や地域のなかで「暮らし」という営みをつづけながら、さまざまな経験や人間関係を重ね、拡げていきます。この暮らしの営みは、必ずしも「めあて」をもたず、人生という悠久の時間のなかにあるともいえるでしょう。
振り返れば、8月号のコウジくんもすでに40年余の人生を歩いてきました。障害を告げられてから、幼児期に通った保育所の支えのなかで、地域の空間や人間関係に親子で歩み出し、地域に見守られながら暮らしてきました。そしてやがて、地域の人たちとのつながりを彼自身が求め、牛乳屋さんや八百屋さんでの「しごと」をすることになったのです。自分の活動を、「ありがとう」と受けとめてもらいながら、そうやって活動することの幸福感を知り、「はりあい」を感じて、学校を出てからの生活の礎をつくりはじめました。
人生を振り返ったときに、発達にとっての画期となったことがみえてくるものです。そのときに自分の活動の意味を感じ、これが自分の暮らしであり仕事なのだという意識をもてるようになっているはずです。それまでの淡々とした生活や労働の日々が、実を結ぶ瞬間です。
そういった長い時間とともにあって、「時間の単位」をもつ療育、教育などは、どんな役割を果たすことができるのでしょう。乳幼児の療育である児童発達支援さえ、その目的を「動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援」(児童福祉法)と定めています。障害のある子どもたちへの指導・支援は、社会生活を営むための技能の習得や適応のためにのみあるのでしょうか。適応とは、自分の生きる環境・社会や、すでに定められたものに適うようにするという意味です。つまり、子どもが受身となってすでにある社会生活の規準を身につけていくことが目的となるわけです。そこに、自分らしい暮らしや人生を創っていくきっかけを見出すことができるでしょうか。
結論を急がずに、私たちも暮らしと人生に視座をおいて、それに対して療育や教育に何ができるのかを考えていきたいと思います。7月号の羽田千恵子さんの実践から「子どもをつなぐ文化のねうち」を考えたのは、その答えを探す試みの一つでした。少し説明を加えておきたいと思います。
文化のねうちって?
かつて出会った脳性マヒによる肢体不自由と知的障害をあわせもつA子さんは、視線はあいにくいのですが、リズミカルな喃語によって気持ちを表出している子でした。発達検査場面では、積木にもはめ板にも手を出さず、私が働きかければ働きかけるほど、天井の蛍光灯に視線が吸い寄せられていきます。
そんなA子さんが、療育のなかで花瓶にお花を生けるときに、すっと手をのばし、茎の向きも少し調整しようとするのです。その姿を見て私は、「検査場面での自分の声かけの仕方が悪いのかな」「私との信頼関係ができていないからかな」と考えたり、「選択的にしか力を発揮できない弱さがある」と理屈づけようとしたりしていました。療育のなかでは、大好きな先生もいるし、お友だちもいて、個別の検査場面とは異なるのは当然です。でも、そのときの私には、彼女にとって思わず手を出したくなる「文化のねうち」には十分に気づけていなかったのです。
その後の発達相談で(その日は“中秋の名月”の翌日でした)、お母さんが「昨日は、家で月見団子をつくって、A子といっしょに花瓶にススキをさしたんですよ。わかってないと思いますけどね」と話されました。「わかってほしい」「できるようになってほしい」というより、そういう生活の一コマを我が子といつくしんでいることがすっと伝わってくるエピソードでした。今思えば、彼女にとって「花を生ける」という行為は、単なる操作ではなく、周りの人とつながっていく価値ある行為であり、幸福感を共有することすら予期していたのかもしれません。
羽田千恵子さんの言う「単に集団を保障するだけでは、一人ひとりのかけがえのない価値を引き出すことはできない、友だちとつながるには、共有できる世界、媒介する文化が必要」という思い、そして、そのために、子どももおとなもそれぞれにもっている「文化的もちあじ」を融合させていく妙味…これからの連載でもまた考えていきたいと思います。
今回の学習参考文献
・深見憲(1999~2017)『ひろしくんの本Ⅰ~Ⅶ』中川書店(博さんの50年余の記録には汲めども尽きぬ示唆があります)。中川書店は、糸賀一雄『糸賀一雄の最後の講義』『福祉の道行』も出版されています。
・白石正久・白石恵理子編(2020)『新版・教育と保育のための発達診断・下巻』
・白石正久・白石恵理子編(8月末発行予定)『新版・教育と保育のための発達診断・上巻』


