連載17回<もう一つの「発達のなかの煌めき」> 第Ⅱ部第5回 最終回
2024年3月 白石正久・白石恵理子
第17回(第Ⅱ部 第5回、最終回)
誰もが自由で
自分らしく生きる未来を創りだすために
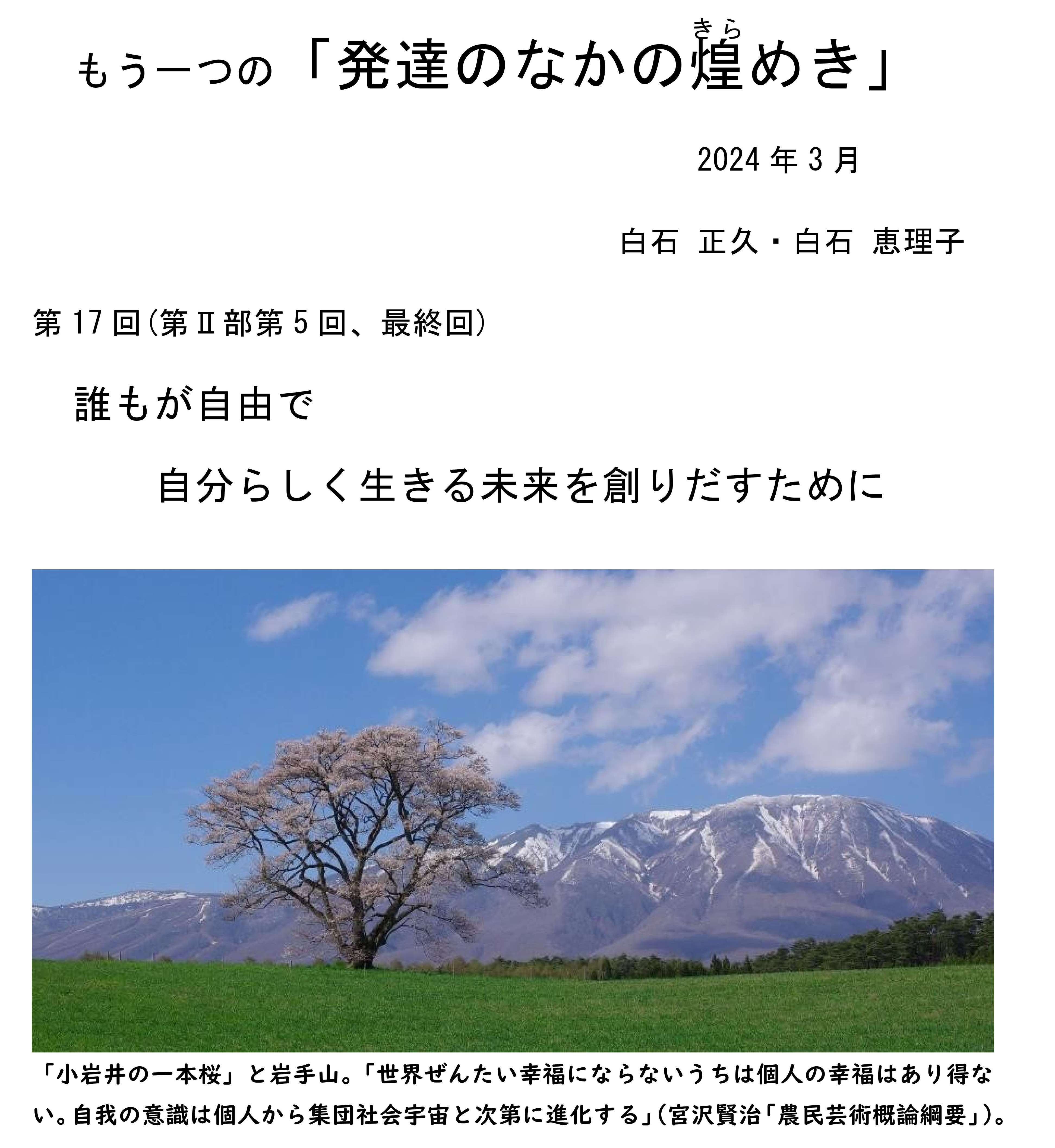
2年間つづけてきた連載「発達のなかの煌めき」は、3月号で無事、最終回となりました。この2年間、お読みくださった皆さん、ご感想・ご意見をお寄せくださった皆さん、「執筆者交流会」にご参加くださった皆さん、そして、地域や職場で「読む会」をつづけてくださった皆さんに心より感謝いたします。この「もう一つの『発達のなかの煌めき』」(以下では「もう一つ」)も今回で最後となります。
最終回ということで、さてさて何を書きましょうか、という話になったわけですが、タイトルである「発達のなかの煌めき」に込めた思いをもう一歩、掘りさげてみたいと考えました。今思えば、この連載を通して、私たちが自分自身に課した課題でもあったのだと思います。それは、一言でいえば、人間の発達をとらえることが、これからの未来社会を創りだす力にどうつながっていくのかということです。
唯物弁証法について
連載の1年目(第Ⅰ部 障害のある子ども・なかまの発達)では、それぞれの発達の時期で努力しつづけている子どもたち・なかまたち一人ひとりのことを想起しながら(ときには、出会ったときには十分に見取ることのできなかった自分の目の貧しさに、情けなさと申し訳なさを感じながら)、発達とは何かを考えてきました。
私たちは学生時代に、田中昌人さんから発達について、「可逆操作の高次化における階層-段階理論」を通して学んできました。それは、ゲゼルやピアジェらによる発達心理学の先行知見をふまえつつ、弁証法的発展のプロセスとしてとらえなおしたものでした。若い私たちにとって、「発達」も「弁証法」も難解きわまりないものでしたが(もちろん、今もそうですが)、でも何か未来につながるような、自分自身や社会への不安を切り拓いてくれそうな魅力をもつ響きでもあったように思います。
では、弁証法的発展のプロセスとはどのようなものでしょうか。弁証法とは、世界のあらゆる事物・事象は、互いに関連しあいながら、たえず運動し、変化・発展し、生成・消滅をつづけているとみる見方です。連載タイトルの「煌めき」は、宇宙に広がる一つひとつの星のイメージにもつながるのですが、宇宙や自然の営みと人間の発達は、深いところで連動しているのです。その連動を以下で考えます。
この、「あらゆるものは、たえず運動し、変化・発展と、生成・消滅を繰り返している」という弁証法的見方の萌芽は、古代ギリシャにまでさかのぼります。古代ギリシャの哲学者たちは、「対話」を重視していました。真剣な対話においては、意見の対立や矛盾が必ず生じ、それを解決するために議論が発展していきます。これは、私たちも日々、実感するところです。弁証法について包括的な論述をおこなったのはヘーゲル(ドイツの哲学者、1770-1831)です。ヘーゲルは、万物は、孤立し静止しているという見方、すなわち自然や社会の事物・事象をバラバラな部分の集まりとみるような機械的な見方に対し、①事物・事象の相互連関や全体をとらえ、②外からの力だけでなく、事物の内部の力による運動をとらえ、③同じ運動のくり返しではなく、進化や発展をとらえました。そして、万物の運動が起きるのは、その事物・事象のなかで生じる矛盾が原動力となり(「対立物の統一と闘争」)、それが「量から質への転換(およびその逆)」をひきおこすこと、そこには「否定の否定」の原則が働いているということを指摘したのです。
*対立物の統一と闘争:あらゆる事物や現象の内部には、たがいに対立し、排除しあう傾向や力が存在している。そのような対立物(矛盾)は互いに他を必要としつつ(統一)闘争しており、それが事物や現象の変化・発展の根本原因であるということ。
*量から質への転換(およびその逆):事物や現象には量的側面と質的側面があり、量の一定の蓄積が質的転換をもたらし、質が変わることによって、新たな量的蓄積をもたらすということ。
*否定の否定:質的転換は、それまでの質との断絶ではなく、その積極的なものは受け継ぐこと(これを弁証法的否定という)。そして低い段階の質的特徴が、高い段階において反復してあらわれる、すなわち「らせん的」といえる発展をみせるということ(否定の否定)。
(この3つを弁証法的発展法則といいます。しかし、これを事物や現象の解釈のための既成のメガネとすることは正しくありません。解釈の手がかりでありつつ、事物や現象の具体的な変化に潜む法則性を明らかにしていくなかで、この発展法則の認識がさらに豊かになっていくという研究の経路を大切にしたいと思います。)
これらは、きわめて重要な歴史的意味をもつ解明でした。しかし、ヘーゲルの弁証法は、精神(人間の似姿としての神)を世界の根源とみる観念論と結びついていました。ヘーゲルは、人間の労働や社会的実践の主体的意義を十分にはとらえていなかったのです。
このヘーゲルの弁証法を受け継ぎ、唯物論的な弁証法につくり変えたのがマルクス(1818-1883、ドイツの経済学者・哲学者・革命家)です。
ヘーゲルの時代に主流であった観念論においては、精神(神)が世界をつくっているという逆立ちが起っていたわけですが、それに対し、自然や社会をありのままにとらえるのが唯物論です。唯物論は、精神のはたらきを認めないのではなく、精神もまた神経系などの物質的基礎をもっていることから出発するものです。
ただ、マルクス以前の古い唯物論では、対象や現実を「客体」として観察するにとどまり、実践として、主体的にとらえてはいませんでした。マルクスは、人間が実際におこなっている労働や社会的実践によって、対象や現実をつくりかえていることに着目したのです。つまり、人間という「主体」が、実践によって、現実の「客体」のなかに入り込むこと、そのことによって、人間自身にも変革が起きるのだということを見抜いたのです。こうした新しい唯物論と弁証法がむすびつくことによって、弁証法的唯物論がうまれました。
人間発達と唯物弁証法
このことを人間の発達にひきよせて考えてみましょう。
実は、ヘーゲル以前に主流であった、万物は孤立し静止しているという見方、自然や社会の事物・事象をバラバラな部分の集まりとみるような機械的な見方は、現在でも発達や教育の考え方のなかに、たびたび顔を出すことがあります。
子どもの姿を、運動面ではどうか、言語面ではどうか、認識面ではどうか、社会性の面ではどうかとバラバラにとらえるだけで終わっていないでしょうか。ある能力だけに焦点をあててくり返し「訓練」し、それで「できるようになった」とみるような保育・教育になっていないでしょうか。こうした発達の見方、保育・教育のとらえ方は、子どもの内なる自然、子ども自身のなかで発達という運動が起こっていることを軽視し、外側から子どもを操作してつくりかえようとする考え方といってもよいでしょう。
また、ヘーゲルが明らかにした、矛盾を原動力にして変化が起きるということ、量から質への転換(あるいはその逆)、否定の否定という3つの原則も、人間の発達をとらえるうえで極めて重要です。矛盾が原動力になるという点は後述しますが、発達には量的側面と質的側面があり、それらは互いの前提となっているという見方は、イメージしやすいと思います。人間の発達の道すじにおいては、量的蓄積(ヨコへの発達)の時期と質的転換(タテヘの発達)の時期がくりかえし訪れます。また、発達の新たな段階では、以前の発達の段階で特徴的であったことが、より高次なものになって、くりかえし「らせん的」にあらわれます。
さらにマルクスが明らかにした、人間は外界を「観察」するだけでなく、外界にはたらきかけ、そのことによって人間自身に変革が起きるというのは、まさに、人間発達そのものを言い表しています。幼い子どもたちも、障害の有無にかかわらず、外界に自分の力ではたらきかけ、その結果を何らかの形で受け取ることによって、手ごたえを得、それが発達につながっていくのです。
そして、人間が発達するのは、その人のなかで「矛盾」を原動力とした「自己運動」が起きるからだと言えるでしょう。保育や教育など外部からのはたらきかけは、この「自己運動」をうながしたり、さまたげたりと、その方向に影響を与えることはできますが、発達の原動力そのものになることはできません。ヴィゴツキー(1896-1934、旧ソ連の心理学者、唯物弁証法を土台に新しい心理学を構築した)が提起した「発達の最近接領域」という考え方は優れた知見ですが、日本では誤った解釈が流布し、子どもにとって、難しすぎず、簡単すぎず、ちょうどよいくらいの抵抗が教育的に与えられることが重要だという浅薄で誤った理解で広まった経緯があります。
子どもにとって、ちょっとだけ難しいことをのりこえることで達成感や満足感につながり、それが次への意欲につながるというわけですが、このとらえ方では、子どもの前に次のハードルを準備しつづけていくという発想に陥りがちです。そうした見方を批判し、田中昌人さんたちは、人間の内部に、発達の原動力がどのように誕生・生成していくのかの解明に力を尽くしました。ひらたく言えば、子どもの前に教育内容がハードルのように用意されるだけで発達という「自己運動」が起こるのではなく、子ども自身がその教育内容を自分の内側に取り込み、「不安だけどやってみたいな」「難しそうだけど面白そうだな」と心が動くことが必要であり、それが発達に必要な「矛盾」になるのです。そして、そのためには、子どもの今に必要な教育内容だけではなく、「不安だけどやってみたいな」「難しそうだけど面白そうだな」と心を前に動かすための支えも必要です。
「可逆操作の高次化における階層-段階理論」では、階層間の移行(質的転換)をなしとげる力として、「新しい発達の力」が誕生することを明らかにしました。通常の場合、4か月頃に「生後第1の新しい発達の力」、10か月頃に「生後第2の新しい発達の力」、5・6歳頃に「生後第3の新しい発達の力」が誕生することは、連載や「もう一つ」で述べてきまた。「新しい発達の力」は、次の大きな発達の質的転換期(「6か月の節」、「1歳半の節」、「9歳の節」)をのりこえていくための大切な力になります。詳細はここでは述べませんが、4か月においては、目の前の相手にむかって「心の窓」が開かれ、微笑みをもって相手との関係を結ぼうとすること、10か月においては、相手の心のなかの意図も感じ取りながら、自分の意図をつくって生活や遊びの主体になろうとすること、5・6歳においては、集団や社会のもつ価値にも気づいたうえで、友だちとつながり、未来の自分もつくろうとすること…こうした力の誕生が「新しい発達の力」です。それらは、いずれも、子どもが相手や社会との関係において、「客体」から「主体」になりかわろうとする心のはたらきとも言えるでしょう。
誰もが自由で自分らしく生きる未来を創りだすために
マルクスが提起したのは、唯物弁証法だけではありません。彼は、エンゲルス(1820-1895、ドイツの社会思想家)とともに、人間の社会と歴史を唯物論的にとらえる「史的唯物論」の研究も進めました(史的唯物論に対して、唯物弁証法を弁証法的唯物論ということもある)。それは、経済学批判の方法ともなり、マルクスの主要な労作である『資本論』にもつながっていきます。
「史的唯物論」の核心となる命題は、①これまでのすべての歴史は、原始共産制を例外として、生産手段をもって支配するものと支配されるものの階級闘争の歴史であり、歴史を階級闘争の見地でとらえなければならない、②たがいに闘争する社会の諸階級は、いつでもその時代の支配者と被支配者などの生産関係や交易関係、つまり経済的諸関係によって生みだされる、③支配、被支配という階級の相互関係を直接規定する経済的諸関係が、人間の社会生活の「現実の土台」をかたちづくっており、それぞれの歴史的時期の法的かつ政治的諸制度ならびに宗教的、哲学的、その他のイデオロギーからなる上部構造の特徴は、結局、この土台の性格を反映し、そこから説明される、という3つにまとめられます。
それまでの歴史観では、歴史は英雄などの個々の人間の動機や意志による偶然の出来事の積み重ねと思われていたことに対し、人間の歴史と社会にも弁証法的な発展法則があることを明らかにしたのです。この「史的唯物論」の確立によって、人間はみずから歴史を推進する道すじをつかむことにもなったと言えるでしょう。連載第Ⅱ部第12回(3月号)でお話しした二つの力の「せめぎあい」とは、階級闘争のことを言いかえたものです。
連載や「もう一つ」では、障害のある子どもたち・なかまたちをめぐる現状について、決して楽観できるものではないことを述べてきました。とりわけ、この間、日本社会を席巻している新自由主義は、福祉も教育も、ひいては人間の命や尊厳すらも「お金次第」にし、人々に格差と分断をもちこもうとしています。もちろん、そうした流れに抗って、人間の「優しさ」「つながり」を大切にしようとする人たちがたくさんいるのも事実です。しかし、そうした善意すらふみにじるような「改革」も、次々に画策されています。いったい誰のための政治なのか、誰のための経済なのか、耳をすまし、目をそばだてて感じ取り、考え、そして心をつないでいくことが今こそ求められているのではないでしょうか。
一人ひとりのねがいを徹底的に大切にしていく発達のとらえかた、そこから見えてくる人間への信頼と未来への希望が、社会全体のものになっていくためには、個人の発達をとらえるまなざしだけではなく、社会そのものの変化を創りだすまなざしと結びつく必要があるのだと、連載を終えた今、強く思います。
連載のむすびに
たとえば「1歳半の節」を越えて、幼児期の発達の階層への質的転換を成し遂げた子どもたちは、「1次元可逆操作」という力を手にして発達の歩みを進めます。しかし、その力がいっそうたしかになっていくためには、その力を大切に守り、生かそうとする社会的関係や環境、つまり教育的関係が必要です。もし、それがなかったならば、せっかくの力も委縮したり形骸化したりしてしまうかもしれません。
歴史も、同じです。日本は、絶対主義的天皇制がひきおこした戦争や国民への専制支配を、悲劇的な結末を踏み台にしてのりこえて、「国民主権、基本的人権の尊重、平和主義」の日本国憲法を手にしました。そのときから、共有の財産としての憲法を守るために、国民には「不断の努力」(憲法第12条)が求められているのです。しかし、その憲法の諸原則を押しつぶそうとする力が、亡霊のように存在しつづけています。それは、まさに二つの力の「せめぎあい」の歴史でした。
連載第Ⅱ部第12回でお話ししたように、障害のある人びとの基本的人権の保障を前進させようとする国民の力は、ゆっくりゆっくりではありますが、大切な前進を遂げてきました。1970年代、私たちが大学生であったころ、学生は学問と共に、社会から問いかけられるようにして自らの価値意識を形成し、階級関係のなかでの自分の立ち位置を模索していました。そして、いつしか全障研の会員や『みんなのねがい』の読者にもなり、それからの人生を歩いてきました。
しかし、時代は変わりました。二つの力の「せめぎあい」を意識させまいとする政治、それとむすびついた教育、そしてそういった「せめぎあい」が社会の本質ではないとするイデオロギーは、その後の若い世代の価値意識を変容させ、自らの立場を問うことからも遠ざけていることでしょう。
だからといって二つの力の「せめぎあい」が、この社会からなくなったのではありません。いやむしろ、くりかえし述べてきたように、新自由主義の台頭の下で、苦しい生活や人生へと追いこまれ、精神的にも孤立する人びとが増えました。さらに、国家間の分断と憎悪、戦争の時代がつづき、憲法の平和原則を崩しつつ、軍事費の増大を不可避とする意識が、意図的に拡げられようとしています。
人間発達が、質的転換を達成したあと、その新しい力を生かし、拡げていく条件や関係を必要とするように、歴史にも質的な発展の後で新しい時代の市民の力を生かし、拡げていく条件が必要なのです。その条件とは何かを問い、それを産みだしていかなければならないのではないでしょうか。
先に述べたように、私たちが若かったころは、二つの力の「せめぎあい」をリアルに認識し、国民の立場、弱くさせられている人の立場に立つのか、それとも支配者の側に立って栄達を望むのかを問いかけてくる社会がありました。全障研も『みんなのねがい』も、その条件のもとで大きくなったのです。社会が、同じねがいをもつ人びとをつないでくれたとも言えるでしょう。
私たちは今、自前で、一つひとつの「つながり」を創るべき時代を生きているのです。そのことへの覚悟が必要です。しかし、それは本当にステキなことではないでしょうか。全障研も『みんなのねがい』も、自分たちの言葉で訴えかけ、一つひとつ拡げていかなければならない。言いかえれば、人とつながりあうために、自分のあり方を問い、自分の言葉で語りつつ発達していくことができるという、自由な意志が生きる段階にあるのだと思います。
そして、そもそも人は、つながって生きたいのではありませんか。それを強要されたり、大きな力で抑えられるのはイヤだけれど、苦しい思いの仲間、この社会のなかで弱くさせられている仲間がいるならば、その人とともに生きてみようとする。
発達においては、自我を誕生させ、たしかな要求の主人公になっていくけれど、それとともに他者にも思いや要求があり、うれしいことも悲しいことも抱えて生きていることを、子どもは知っていきます。そして、視座を他者に転じて、他者のことを想いつつ、自分自身を省みていく力を発達させていきます。
かつてそのことを、「思いを一つにするという意味でのcompassion(共感)、つまり他者への思いやりをもった寛容で度量のある人格」(『発達をはぐくむ目と心』全障研出版部)と表現してみました。人間の大切な本質であり、互いにはたらきかけあい、力をあわせる実践のなかで、あらわれ出るのだと思います。
それを信頼して、職場の同僚や地域の仲間に、子どもたち・なかまたちの発達へのねがいをわかりあうために、『みんなのねがい』をいっしょに読みませんかとはたらきかけてみよう。連載の最後に、私たちはそう呼びかけました。そして、生活や労働の苦しさの背景にあるものを語りあい、学びあって、一人ひとりがより良い社会を創るための「社会の主人公」になっていこう。そうも呼びかけました。
それに応えて手をつないでくれた仲間、そして、はたらきかけた仲間は、タカラモノです。一人の同僚が全障研の会員になってくれた、『みんなのねがい』を購読してくれたという、その「一人」のことを、全国の仲間と喜びあえるような全障研であってほしいと思います。
では、3月2日の最後の「執筆者交流会」で読み上げた糸賀一雄さんの言葉を紹介して、むすびといたします。
世の中にきらめいている目もくらむような文明の光輝のまえに、この人びとの放つ光は、あれどもなきがごとく、押しつぶされている。その光は異質の光なのである。文明の輝きになれた目には、その異質の光は、光としてうつらないかもしれない。
しかし私たちは、この人たちの放つ光を光としてうけとめる人びとの数を、この世にふやしてきた。異質の光をしっかりとみとめる人びとが、次第に多くなりつつある。人間のほんとうの平等と自由は、この光を光としてお互いに認めあうところにはじめて成り立つということにも、少しずつ気づきはじめてきた。この異質の光をみとめるというはたらきは、なにか特別な能力であるかのようであるが、じつは決してそうではない。いつの世にも、そしてだれにもそなわっているのである。しかしその能力は、あやまった教育と生活のために、長いあいだ隠されており、はたらきがにぶってしまったのである。
精神薄弱な人びとと、そうでない人びとが、この異質の光の照らす世界では、時として優劣は逆転するかもしれない。いや、これまで自分が優れていると思っていた人びとが、この光の照らす世界にきて、その優越感をかなぐり捨てて謙虚になるというだけのことである。優劣といった競いあう心ではない。排他的でないところに、この光の照らす世界の特質がある。釈尊の説くような、真実の「あきらめ」がある。
みせかけの科学的というかけ声に酔って、現実の悩みをひとごとにしてしまってはいけない。この悩みや呻き声に耳を傾けること、それへの共感の心情をたっぷりもって、そして改めてこの人びとと共に生きてみることである。そこにかすかではあるが、この世ならぬ、一条の光が放たれていることに気づかされるのである。この光は、新しい「世の光」である。それはこの人びとから放たれているばかりではなく、この人びとと共に生きようとしている人びとからも放たれているのである。
(生前未発表原稿、糸賀一雄『福祉の道行-生命の輝く子どもたち-』中川書店、2013年)
(白石註) 釈尊の説く真実の「あきらめ」とは、仏教の教え。人間の苦悩は自己中心的な欲望と無知に発する。そのことをありのまま見つめる(諦める、諦観する)ことができれば、解決の方法や真理に近づくことができるとする。キリスト者であった糸賀にあっては、「喜ぶ人とともに喜び、泣く人とともに泣きなさい。思いあがることなく、互いに思いを一つにし、小さくされた仲間とあゆみをともにするのです。自己中心になってはいけません」(「ローマの教会の人びとへの手紙」、本田哲郎氏訳)というパウロの言葉でもあったろう。
学習参考文献
牧野広義『世界は変えられる-マルクスの哲学への案内』学習の友社、2016年


